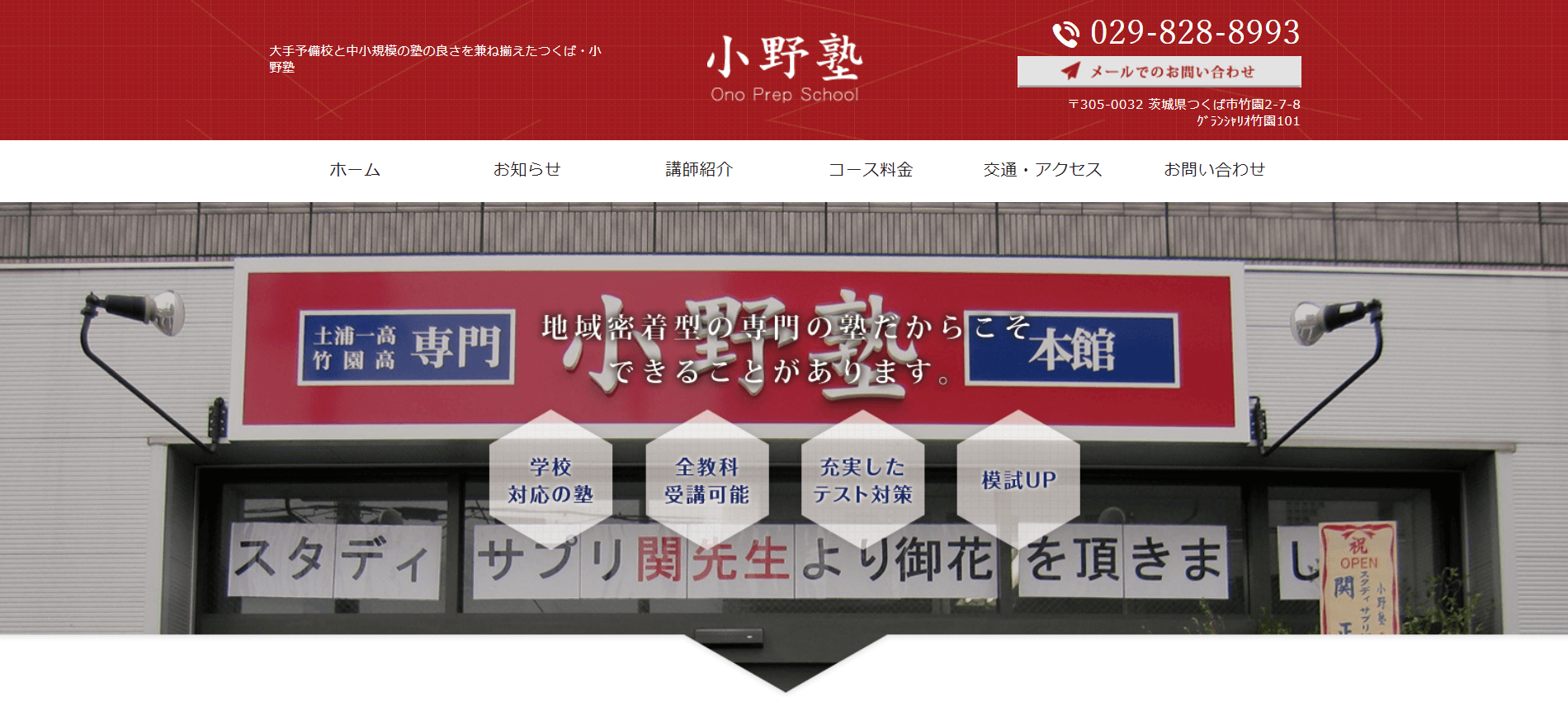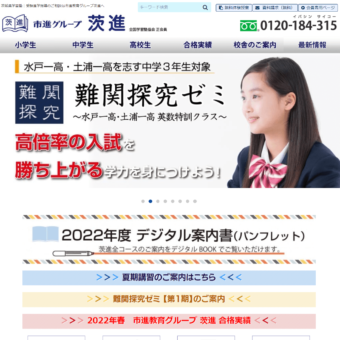古文・漢文が苦手な人必見!おすすめの勉強手順を紹介

古典は、現代の日本語と似ているからといって、感覚だけで解けるような科目ではありません。むしろ、英語のように「別の言語」として認識し、段階を踏んで習得することが重要です。本記事で「古文・漢文を解くために必要な力」と、それぞれの科目で効果的な勉強手順をくわしく解説するのでぜひ参考にしてください。
古文・漢文を解くために必要なこと
まずは、古文・漢文を読み解くコツを見ていきましょう。
単語・文法の知識
古典における単語や文法は、現代語と共通する表記であっても意味や使い方がまるで異なります。そのため、古典を読み解くにはまず「古典語の語彙」と「文法」の基礎知識を身につけることが不可欠です。
現代の感覚に頼って読解を始めてしまうと、誤読の原因になります。よくある失敗は「とりあえず問題集を解いてみる」ことです。しかし、知識が伴っていない状態でこの勉強をすると、効率的な学習にはなりません。まずは単語と文法の土台を固めることから始めましょう。
古文・漢文常識の理解
古文・漢文には、それぞれの時代背景や文化、風習が色濃く反映されています。こうした「古文・漢文常識」が頭に入っていれば、作品の意図や登場人物の行動が理解しやすくなり、読解力の向上につながります。たとえば、貴族社会における男女関係、仏教思想、儒教道徳といった価値観を理解していれば、設問の意図を読み違えることも減ります。
読解力の養成
単語・文法・常識を学んでも、それだけで得点が伸びるわけではありません。最終的に求められるのは、文章を速く、正確に理解する「読解力」です。とくに大学入試や共通テストでは、制限時間の中で多くの情報を読み取り、正確に答える力が求められます。問題演習を重ね、古典文に慣れることでスピードと精度を養いましょう。
古文の勉強のコツ
古典の難しさをわかっていても、問題を解けるかどうかはまた別問題です。古文の勉強のコツも知り、きちんと対策をしなければなりません。ここでは2つのステップにわけて解説します。
STEP1:単語・文法の暗記
古文の学習は、まず「単語」と「文法」から始めるのが鉄則です。古典単語には、現代語と意味が異なるものや、多義語(複数の意味をもつ語)も多数存在します。たとえば「うつくし」と現代語では「美しい」という意味になりますが、古文でいうと「かわいらしい」という意味になります。
「はづかし」も、現代では「恥ずかしい」という意味ですが、古文では「立派だ」という意味になるのです。こうした違いを理解せずに読むと、本文の意味を正反対に解釈してしまうこともあるため要注意です。古文単語は約300語を目安に暗記すると、入試で必要とされる基礎はカバーできます。
市販の単語帳を活用したり、自分専用のノートを作って毎日コツコツと覚えましょう。音読しながら覚えると記憶が定着しやすく、耳からのインプットにもなります。文法においては「動詞の活用形」「助動詞・助詞の意味と用法」「識別のルール」がとくに重要です。
たとえば「秋きぬと(秋が来た)」と「 秋こぬと(秋が来ない)」という文では「と」の上が終止形か未然形かで意味が変わるため、活用の識別ができるようになると読解の正確性が格段に上がります。
STEP2:長文読解の演習
単語と文法をある程度習得したら、次は実践的な長文読解に取り組みましょう。古文には主語が省略されていることが多いこと、そして敬語の方向(誰が誰に敬意を払っているか)がわかりにくいという特徴があります。
最初は戸惑うかもしれませんが、これらを読み解くには、文章全体の流れをつかむ練習が必要です。演習問題を通して、読解の手がかりとなる文法や語彙、背景知識を総動員しましょう。何度も解いて復習することで、自然と長文を読み慣れていき、古文常識も身についていきます。
漢文の勉強のコツ
漢文は中国で生まれたものがほとんどで、日本語とはまた異なる特徴をもちます。また、作品から読み取れる感覚の違い、時代背景も理解したうえで問題に取り組みましょう。
STEP1:句法の暗記
漢文は漢字のみで構成された文体であり、日本語と異なる語順・構文が使われています。まずは「訓読(返り点や送り仮名を用いて読み下す方法)」を理解することが第一歩です。訓読を正しく理解するためには、句法の暗記が不可欠です。たとえば、以下のような基本句法をまず押さえましょう。
・「使役」:~をして…せしむ(使A〜Bせしむ)
・「否定」:~ず(不〜)
・「疑問・反語」:〜か、いづくんぞ〜(何ぞ〜)
漢文の平均点は共通テストで5〜6割とされ、難易度はそれほど高くありません。句法と書き下し文の変換ができるようになれば、安定して高得点を狙える科目です。句法は書き下し文の形で覚えると、返り点や語順も同時に理解でき、より実践的な力がつきます。こちらも音読を取り入れると効果的です。
STEP2:長文読解の演習
句法に慣れてきたら、実際に長文を読みながら訓読力と読解力を磨きましょう。おすすめの方法は、まずは書き下し文に直す、そして意味を自力で訳すというものです。解説や模範解答と照らし合わせて確認して、また同じ問題に繰り返し取り組むことで、意味を丁寧に読み取る訓練ができ、確実に力がついていくでしょう。
まとめ
古典を攻略すれば、国語の得点力がぐっと上がります。漢文・古文にかかわらず、古典は感覚ではなく「論理」で読み解く科目です。英語のように、まずは単語や文法の基礎をしっかり身につけ、その上で長文に慣れていくという段階的な勉強法が必要です。また、長文問題は入試での配点が高く、実践的な得点源となる分野となるため、演習問題を繰り返し解き、解説と照らし合わせて読解の精度を高めましょう。もしひとりで勉強を進めるのが難しいと感じたら、学習塾の力を借りるのも有効です。苦手を克服し、自信をもって入試本番に臨めるよう、今から計画的に取り組んでいきましょう。
-
 引用元:https://onojuku.net/
大手予備校と中小規模の塾のメリットを兼ね備えた地域密着型の学習塾です。
引用元:https://onojuku.net/
大手予備校と中小規模の塾のメリットを兼ね備えた地域密着型の学習塾です。-
Point
地域密着型の学校対応授業
-
Point
大手と個人経営のメリットを両立したハイブリッドな指導
-
Point
充実したテスト対策と高い実績
-
Point